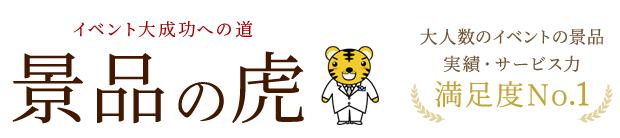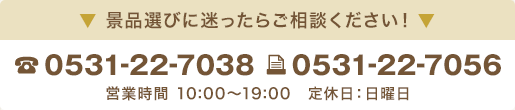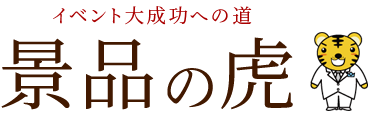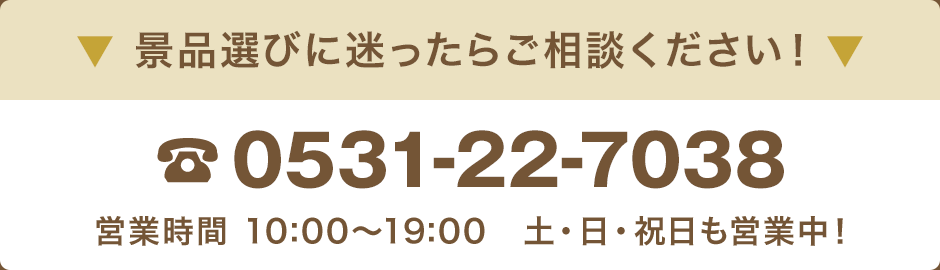お役立ちコンテンツ
忘年会の司会で使える挨拶・セリフ例と成功のポイント
「忘年会の司会を任されたけど、何を話せばいいのかわからない」「進行がグダグダになったらどうしよう」そんな不安を抱えている方は多いでしょう。忘年会の司会は、事前にしっかりと準備をしておけば決して難しいものではありません。
この記事では、司会進行の基本的な流れから、そのまま使える台本、参加者に喜ばれる進行のコツまで、初心者でも安心して取り組める内容を紹介します。
忘年会の司会に求められる役割
忘年会の司会は、ただ進行を読み上げるだけではありません。 会の流れを心地よくスムーズに進めることが、まず大切な役割です。限られた会場時間や参加者の予定を意識しながら、プログラムごとの時間配分を工夫して進行していきます。
さらに、思わぬハプニングが起きたときに落ち着いて対応できることも、司会の腕の見せどころです。機材のトラブルや進行の遅れがあっても、その場の雰囲気を大切にしながら柔軟に切り替えていく力が求められます。
また、送迎バスや二次会の案内、お手洗いの場所など、参加者に安心して楽しんでもらうためのアナウンスも大切な役割のひとつです。
忘年会の基本的な流れ
忘年会の司会を成功させるためには、まず全体の流れを把握しておくことが重要です。一般的な忘年会は、以下のような流れで進行されます。
-
1. 開会宣言(司会者)
忘年会の開始を告げる重要な第一声です。
-
2. 開会の挨拶(最も立場の高い人)
社長や部長など、参加者の中で最も上位の方による挨拶です。
-
3. 来賓の挨拶(社外ゲストがいる場合)
取引先など、社外からの参加者がいる場合に行います。
-
4. 乾杯
3番目に立場の高い人、または開会の挨拶と兼任する場合があります。
-
5. 食事・歓談
参加者が食事を楽しみながら交流する時間です。
-
6. 余興・表彰式
ビンゴ大会、カラオケ、ゲームなど、会を盛り上げるメインイベントです。
-
7. 中締め
2番目に立場の高い人による締めの挨拶と手締めです。
-
8. 閉会宣言(司会者)
忘年会の終了と二次会の案内を行います。
【台本付き】忘年会の司会進行で使える挨拶・セリフ
ここからは、忘年会の各場面で使える具体的なセリフ例を紹介します。そのまま使える台本として活用してください。
1:開会宣言
開会宣言は、忘年会のスタートを知らせる大切な役割です。まずは参加者のみなさんの気持ちを集め、会場全体の空気を和やかに整えるところから始めてみましょう。
【フォーマルな場合】
皆様、大変お待たせいたしました。
本日はお忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございます。
ただいまより、令和6年、株式会社○○の忘年会を開催いたします。
本日司会を務めさせていただきます、○○部の○○です。
初めての司会で緊張しておりますが、皆様と楽しいひとときが過ごせるよう精一杯努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
【カジュアルな場合】
皆様、お待たせいたしました!
これより令和6年、株式会社○○の忘年会をスタートします!
本日の司会を担当させていただく○○部の○○です。
今年一年を振り返りながら、ワイワイと楽しい忘年会にしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします!
明るくはっきりとした声で、参加者全員に聞こえるよう話すのがポイントです。「緊張していることも含めて自分らしさ」と捉え、素直な気持ちを表現しましょう。
2:開会の挨拶(最も立場の高い人によるスピーチ)
開会の挨拶では、社長や上司の紹介を正確に行うことが何より大切です。
【社内のみの場合】
それでは開会にあたり、○○社長よりご挨拶をいただきます。
○○社長、よろしくお願いいたします。
(挨拶終了後)○○社長、ありがとうございました。
【社外参加者がいる場合】
それでは開会にあたり、弊社代表取締役社長○○よりご挨拶を申し上げます。
(挨拶終了後のお礼は省略して、スムーズに次へ進行します)
役職名や名前は間違えると失礼にあたるため、必ず事前にしっかり確認しておきましょう。読み方が難しい場合は、ふりがなを添えておくと安心です。また、挨拶の持ち時間は1〜3分程度などと事前に伝えておくことが重要です。
3:来賓の挨拶(社外ゲストがいる場合)
社外からの参加者がいる場合は、来賓として特別に紹介します。
続きまして、本日は貴重なお時間をいただき、○○会社の○○様にもご参加いただいております。
○○様より一言ご挨拶をいただけますでしょうか。○○様、よろしくお願いいたします。
(挨拶終了後)○○様、お忙しい中貴重なお話をありがとうございました。
来賓が複数いる場合は、まず一番立場の高い方にご挨拶をお願いするのが基本です。その際には持ち時間は1〜2分程度といった目安を事前に伝えておくとスムーズです。
4:乾杯
乾杯は、忘年会の雰囲気を一気に盛り上げる大切な瞬間です。参加者全員がグラスを手にして準備が整ったのを確認してから、元気よくスタートしましょう。
【基本パターン】
それでは乾杯に移らせていただきます。乾杯のご発声は○○部長にお願いいたします。
皆様、お手元のグラスをご用意ください。
○○部長、よろしくお願いいたします!
(乾杯終了後)○○部長、ありがとうございました!
【盛り上げたい場合】
さあ、いよいよお待ちかねの乾杯です!
今年一年の労をねぎらい、来年への飛躍を願って、皆様で盛大に乾杯しましょう!
乾杯のご発声は○○部長にお願いいたします。
皆様、グラスの準備はよろしいでしょうか?
司会者も一緒に元気よく「乾杯!」の声に参加しましょう。
5:食事・歓談
乾杯が終わったら、いよいよ食事とおしゃべりを楽しむ時間です。ここではあれこれ話しすぎず、シンプルにアナウンスして進めましょう。
それでは皆様、お料理とお酒をお楽しみください。
普段なかなかお話しできない方とも、ぜひこの機会に交流を深めていただければと思います。
この後、○時頃から余興もご用意しておりますので、お楽しみに!
また、お手洗いに行かれる方は、会場を出て右手の奥にございます。
喫煙をされる方は、1階の喫煙所をご利用ください。
親切なアナウンスは、参加者にとても喜ばれます。会場施設の案内を伝えたり、このあと控えているプログラムへのちょっとした期待感を添えるひと言を入れると、より雰囲気が和みます。
6:余興・表彰式
余興は、忘年会の盛り上がりをぐっと高めるメインイベントです。とくに景品がある場合は、その紹介の仕方ひとつでワクワク感が大きく変わります。
【ビンゴ大会の場合】
お食事も進んでまいりましたが、皆様お待ちかね、今年も豪華景品が当たる大ビンゴ大会のお時間がやってまいりました!
今年の景品は例年以上に気合を入れてご用意いたしました。
まずは特賞から発表させていただきます!
なんと特賞は、憧れの○○です!
こちらは定価○万円の超豪華商品でございます!
そして1等賞品は…皆様の生活を豊かにしてくれる○○セット!
実用性抜群で、きっとご家族の皆様にも喜んでいただけることでしょう!
景品の紹介では「価値」「魅力」「使用場面」を具体的に伝えることがポイントです。「これは欲しい!」と思わせる紹介で、会場の盛り上がりは格段に変わります。
【カラオケ大会の場合】
続いて、毎年恒例のカラオケ大会に移らせていただきます!
今年のトップバッターは、美声の持ち主○○さんです!
披露していただく楽曲は、話題沸騰中の○○(歌手名)の○○(楽曲名)です!
皆様、温かい拍手と声援でお迎えください。○○さん、よろしくお願いいたします!
【表彰式の場合】
それでは、今年度の優秀な成績を収められた方々の表彰式を行います。
今年も多くの方が素晴らしい実績を残してくださいました。
まずは営業成績優秀賞から発表いたします…
余興は、司会者の盛り上げ方ひとつで会場の熱気がぐんと変わります。大げさなくらいのリアクションで、参加者をぐいぐい引き込んでいきましょう。
景品の虎では、忘年会を盛り上げる景品を幅広くご用意しております。ぜひご利用ください。
7:中締め
中締めは、早めに帰宅する参加者のための区切りとなる重要な時間です。
皆様、楽しい時間はあっという間ですね。
宴もたけなわでございますが、ここで○○専務より中締めの挨拶をいただきたいと思います。
○○専務、よろしくお願いいたします。
(挨拶終了後)○○専務、ありがとうございました。
中締めでは手締めを行うことが多いため、事前に確認しておきましょう。一本締め、三本締め、万歳三唱など、会社の慣例にしたがって進行します。
8:閉会宣言
忘年会の最後を飾る閉会宣言では、感謝の気持ちと来年への期待を込めて締めくくります。
皆様、本日は株式会社○○の忘年会にご参加いただき、誠にありがとうございました。
つたない司会進行ではございましたが、皆様のおかげで盛況のうちにお開きとなりました。
これにて令和6年の忘年会を終了させていただきます。
今年一年、本当にお疲れさまでした。
来年も皆様とともに素晴らしい一年にしていきましょう!
なお、この後○時より○○にて二次会を予定しております。お時間の許す方はぜひご参加ください。
お帰りの方は、お忘れ物のないよう気をつけてお帰りください。
本日は本当にありがとうございました!
二次会の案内はできるだけ具体的に伝えつつ、帰宅される方への気配りも忘れないようにしましょう。
忘年会までに司会が準備すること

ここでは当日までに準備しておくべき重要なポイントを紹介します。
会場の状況をチェックする
まず最初に、会場の詳細を把握しましょう。会場の広さ、音響設備の有無、司会者の立ち位置などを確認します。
座敷の会場なら座ったままでの進行、立食形式なら立ちながらの進行など、会場の形式によって司会の立ち振る舞いが大きく変わります。
マイクがある場合は事前に音量テストを行い、ない場合は声の届く範囲を把握しておきましょう。「声が小さくて後ろまで聞こえなかった」というトラブルは事前チェックで防げます。
台本を作成する
スムーズに進行するためには、あらかじめ台本を作っておくことが大切です。完璧を目指すよりも、スケジュールどおりに進行することを最優先に作成しましょう。
時間配分を明記し、各プログラムの開始予定時刻を記載しておくと、進行の遅れに気づきやすくなります。また、トラブルが起きた際の時間調整方法も考えておきましょう。
台本には「このどおりに読めば大丈夫」という安心感があります。緊張で頭が真っ白になっても、台本があれば必ず乗り切れます。
登壇者の役職と名前を確認しておく
重要な準備のひとつが、登壇者の正確な情報確認です。役職名、氏名の読み方、略歴などを事前にしっかりと確認しておきましょう。
とくに普段接点のない役員の方や、社外からの参加者の情報は入念にチェックが必要です。読み方が難しい名前にはふりがなを振り、間違いのないよう準備しましょう。
運営メンバーと打ち合わせをしておく
司会者一人で忘年会を成功させることはできません。幹事チーム、会場スタッフとの連携が不可欠です。
タイムキーパー、受付担当、会場準備係など、それぞれの役割分担を明確にし、当日の動きを共有しておきましょう。
こちらの記事では、忘年会のお知らせについて解説しています。例文や必要な記載事項も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
司会経験者に話を聞いて対策する
司会を経験した人からのアドバイスは、とても心強いものです。過去に司会を務めた先輩や同僚に、実際にあったトラブルや成功のコツを聞いてみましょう。
「マイクの電池が切れた時はどうしたか」「プログラムが大幅に遅れた時の対処法」など、実体験にもとづくアドバイスは教科書では学べない貴重な情報です。
さらに、会社ならではの慣習や参加者の雰囲気なども聞いておくと安心です。こうした事前の情報収集が、当日の自信につながります。
忘年会の司会を成功させるためのポイント
事前準備ができたら、次は当日の心構えとテクニックです。以下のポイントを意識して司会に臨みましょう。
明るく元気に振る舞う
「完璧にやろう」と考えすぎず「みんなで楽しもう」という気持ちで臨むことが大切です。多少のミスがあっても、明るい笑顔でフォローすれば参加者は温かく受け入れてくれます。
常に笑顔を心がけ、はきはきとした話し方を意識しましょう。
早口にならないよう気を付ける
緊張すると誰でも早口になりがちです。とくに司会の経験が少ない方は、ゆっくり話すことを心がけましょう。
自分が思っているよりも2倍くらいゆっくり話すつもりでちょうどよいペースになります。深呼吸をして、一文ずつ区切って話すことを意識してください。
スケジュール通りに進行させる
時間管理は司会者の最も重要な役割です。各プログラムの時間を常に意識し、遅れが生じたら適切に調整しましょう。
トラブルが起きても冷静に対処する
機材の不調、プログラムの変更、参加者の体調不良など、忘年会ではさまざまなトラブルが起こり得ます。
そんなときこそ、司会者の真価が問われます。慌てずに冷静に状況を判断し、参加者に適切にアナウンスしましょう。「トラブルは想定内」という気持ちで臨むことが大切です。
ウケを狙いすぎないようにする
会場を盛り上げたい気持ちは大切ですが、無理にウケを狙う必要はありません。どうしてもユーモアを交えたい場合は、開会や閉会の挨拶で軽いジョークを一言そえる程度に留めましょう。
身内ネタや会社の出来事を織り交ぜると、参加者に親しみを感じてもらえます。
ただし、特定の人をからかったり、不適切な内容は避けることが重要です。「笑顔」と「温かい雰囲気」を大切にした進行を心がけましょう。
まとめ
忘年会の司会は、事前の準備と当日の心構え次第で成功させることができます。台本を用意し、会場の状況を把握し、関係者との連携を密にすることで、スムーズな進行が実現できるでしょう。
大切なのは、参加者全員に楽しんでもらいたいという気持ちです。完璧を求めすぎず、明るく元気に、そして時間を意識した進行を心がければ、きっと「今年の忘年会は楽しかった」と言ってもらえる素晴らしい会になります。
忘年会を盛り上げるには、やっぱり魅力的な景品が欠かせません。参加者全員が笑顔になれるような豪華な景品選びは「景品の虎」におまかせください。予算に合わせてさまざまな景品を選べるため、参加者に喜ばれる一品を手軽にそろえられます。
「どんな景品を選べばいいか迷う」という幹事様には、人気の「景品お任せコース 」もおすすめです。忘年会をさらに盛り上げる特別な景品で、参加者の皆様に喜びをお届けしましょう。