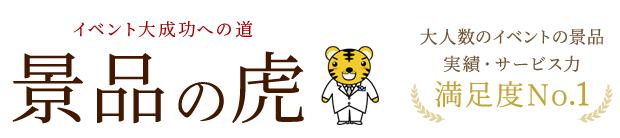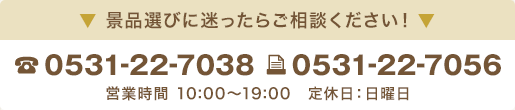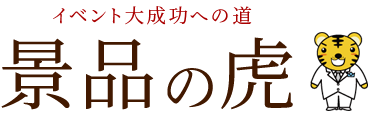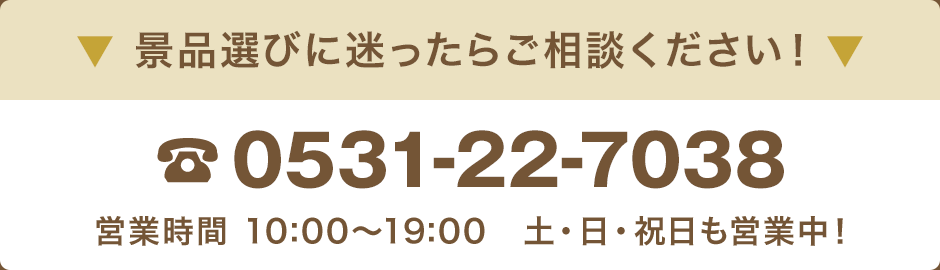お役立ちコンテンツ
忘年会の予約はいつから?日程の決め方や注意することを紹介
忘年会の幹事に任命され「いつ頃から予約すればいいの?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。忘年会をスムーズに成功させるには、日程調整や会場選びのコツを押さえておくことが大切です。
本記事では、忘年会シーズンの時期や日程の決め方、会場選びで注意すべきポイントをわかりやすく紹介します。また、忘年会をさらに盛り上げる景品選びについても解説していますので、ぜひ参考にしてください。
忘年会の時期はいつから?

初めて幹事を任された方や経験が少ない方にとって、日程の設定は悩みどころのひとつです。まずは、一般的に忘年会が開催される時期を把握することから始めましょう。
忘年会シーズンは12月中旬から
一般的に、忘年会が最も多く開催されるのは12月中旬以降とされています。なかでも、12月第2週から第3週にかけてがピークのタイミングです。
12月下旬に実施するケースもありますが、年末が近づくにつれて仕事やプライベートの予定が立て込み、参加が難しくなる人も出てきます。そのため、忘年会はあまり年末ギリギリの日程を避けて設定するのがおすすめです。
早めに開催する場合は?
12月中旬の忘年会シーズンは、どの飲食店も混雑しやすく予約が取りづらくなる傾向があります。そのため、混雑を避けたい場合は、開催時期を少し早めるのもおすすめです。11月下旬であれば、少し早めの忘年会として違和感なく実施できます。
実際、多くの居酒屋や飲食店では、11月後半から忘年会向けのプラン提供を始めています。12月に入るとほかの予定と重なり参加が難しくなる人も増えるため、参加率を高めたい場合には、余裕を持って早めの開催を検討してみましょう。
忘年会の予約や準備はいつからするべき?
忘年会の予約は、シーズンである12月の約2か月前、10月頃が予約の目安とされています。少人数の忘年会であっても、開催日の1か月前までには済ませておくのが基本です。とくに12月中旬のピークに予定している場合は、11月中旬までに予約を完了させておくと安心です。
参加人数が多かったり、貸切が必要だったり、人気のあるお店を希望する場合は、より早めに予約しておきましょう。直前になると予約が取りづらくなるため、いくつかの候補をあらかじめリストアップし、余裕をもって予約を進めておくとスムーズです。
忘年会の日を決める流れ
忘年会の日程は、参加メンバーの予定を把握したうえで調整するのが基本です。よりスムーズに開催日を決められるよう、日程決定までの流れを紹介します。
参加者の日程を確認する
まずは、参加予定者のなかでも役職者のスケジュールを最優先で確認しましょう。上司が不在のまま部下だけが盛り上がる忘年会になってしまうと、後々気まずい雰囲気になる可能性があります。
役職者が参加できる日を3〜4日ほど候補として挙げておくのがコツです。初めから日程を一日に絞ってしまうと、急な予定変更に対応できなくなるため、複数の候補日を用意しておくと安心です。
また、取引先など外部のゲストを招く場合には、その人のスケジュール確認も忘れずに行いましょう。
候補日を決めてアンケートをとる
役職者や取引先のスケジュールをもとに候補日をいくつか絞り込んだら、その他の参加者にもアンケート形式で都合のよい日を確認しましょう。このとき、回答期限を「◯月◯日まで」と明確に設定することが重要です。
期限を設けないと回答が遅れ、希望していたお店の予約が取れなくなるリスクがあります。朝礼やチャットツールなどを活用し、複数回アナウンスして確実に全員から回答を集めるようにしましょう。
日にちが決まったら予約する
アンケートの結果をもとに、できるだけ多くの人が参加できる日を選んで日程を確定させましょう。すでに候補の店舗がある場合はすぐに予約します。まだ決まっていない場合は早急に店探しを始めます。
オンライン予約が可能な店舗なら、居酒屋予約サイトやアプリを使って、日時や人数を入力するだけで簡単に手続きできます。ただし、コース内容の変更や座席配置など細かい要望がある場合は、電話で直接伝えましょう。
また、混雑する時間帯は電話がつながりにくいため、比較的余裕のある16時〜18時頃に連絡するのがおすすめです。
忘年会の予約をする際に注意すること
忘年会の会場を予約する際には、事前に確認しておくべき点がいくつかあります。幹事として当日の進行をスムーズに進めるためにも、注意点をしっかり押さえておきましょう。
参加者全員が楽しめるお店を選ぶ
忘年会の会場選びでは、趣旨や参加者層に応じたお店を選ぶことが大切です。
たとえば、同僚だけの気軽な集まりであれば、カジュアルでにぎやかな雰囲気の居酒屋などでも問題ありません。しかし、役職者が参加する場合は、落ち着いた雰囲気の店のほうが好まれる傾向があります。
とはいえ、格式が高すぎると一般社員が気後れしてしまうこともあるため、誰もが気兼ねなく楽しめるようなバランスの取れたお店を選びましょう。
また、参加人数に見合った店の広さも重要です。大人数の場合は貸切ができる店や広めの宴会場を検討しましょう。少人数であっても、できれば半個室よりも完全個室の方が落ち着いて会話や食事を楽しめます。
余興やイベントを予定している場合には、マイクやスピーカーなどの設備が利用できるか事前に確認しておくと安心です。
加えて、会場の「アクセスのよさ」も忘れてはいけないポイントです。会社から遠すぎると移動の負担が大きくなるため、会社近辺や主要駅近くの店舗を選ぶと参加しやすくなります。車での来場が多い場合は、駐車場の有無も確認しておきましょう。
さらに、二次会を予定している場合には、近隣にカラオケやバーがある店を選ぶと、移動がスムーズになります。
下見をする
会場の候補が決まったら、実際にお店へ足を運んで下見をするのがおすすめです。最近ではネットで店内の写真や口コミを簡単にチェックできますが、実際の雰囲気や設備は行ってみないと分からないことも多いです。
料理の内容だけでなく、テーブルの配置や個室の広さ、スタッフの対応なども重要なチェックポイントです。とくに個室は、見た目以上に狭く感じることもあるため、参加者が快適に過ごせる広さかどうかを自分の目で確かめておきましょう。
もっとも一般的な下見方法は、営業時間中に客として訪れることですが、その分飲食代がかかる点には注意が必要です。費用を抑えたい場合は、事前に店舗へ連絡して、混雑する時間帯を避けての見学が可能か相談してみるのもひとつの方法です。
キャンセル料の条件を確認する
お店によっては、予約日の数日前からキャンセル料が発生することがあります。会社の忘年会では、家庭の事情などによって急な欠席が出る可能性もあるため、あらかじめキャンセルの規約をしっかり確認しておきましょう。
参加者から自主的にキャンセル料を申し出てくれれば問題ありませんが、なかには負担に納得せず不満を抱く人もいます。お金に関するトラブルを防ぐためにも、幹事は事前にキャンセル規定を全員に周知しておくことが大切です。
たとえば「3日前のキャンセルで料金の20%」「当日のキャンセルは全額負担」など、具体的な内容をメールや書面で伝えましょう。また「◯月◯日以降はキャンセル料が発生するため、欠席の場合は早めにご連絡ください」といった注意喚起もそえると効果的です。
口頭だけの伝達では「聞いていなかった」と後からトラブルになる可能性があるため、記録に残る方法(メール・社内チャットなど)での案内が望ましいです。
さらに確実なのは、事前に会費を徴収しておくことです。万が一、直前キャンセルが発生した場合は、そのなかからキャンセル料を差し引いて返金できます。
コースや飲み放題メニューを予約する
大人数での忘年会には、コース料理や飲み放題プランのあるお店を選ぶのがおすすめです。個別注文にすると、料理選びに時間がかかるだけでなく、幹事が注文を取りまとめる手間も増えてしまいます。
コース料理を選ぶ際は、品数やボリュームが十分かどうかを事前に確認しておきましょう。料金が安すぎると料理内容に物足りなさを感じることもあるため、予算と内容のバランスを見極めることが大切です。
飲み放題は、店によってアルコールのラインナップに違いがあります。ビールや焼酎、日本酒など定番メニューのほかに、カクテル系の甘いアルコールドリンクがあるかどうかも確認しましょう。
また、全員がアルコールを飲むとは限らないため、ジュースやお茶、ノンアルコールカクテルなど、ソフトドリンクの充実度も考慮してお店を選ぶと、より多くの参加者が満足できる忘年会になります。
お得なプランがあるか確認する
忘年会向けに「早期予約割引」や「〇名以上の利用で10%OFF」といった特典を用意しているお店もあります。こうした割引を活用すれば、全体の予算を抑えることができ、浮いた分を二次会や景品代に回すことも可能です。
予算管理の面でもメリットが大きいため、予約前にお得なプランやキャンペーンの有無をチェックしておくのがおすすめです。
予約は遅くても1か月前までに済ませておく
開催日が近づくほど人気店の予約は埋まりやすくなり、希望していたお店が利用できなくなる可能性が高くなります。結果的に、料理や雰囲気がいまいちのお店を選ばざるを得なくなることもあります。
そうした事態を避けるためにも、忘年会の予約は遅くとも1か月前には済ませておくのが安心です。早めの行動が、満足度の高い会場選びにつながります。
忘年会の景品を選ぶポイント
忘年会では、ゲームや抽選会などの企画で場を盛り上げるケースがよくあります。とくに景品を用意すると、参加者のテンションも自然と上がり、会全体がより楽しい雰囲気になります。
ここでは、景品を選ぶ際に押さえておきたいポイントを項目別に紹介します。
金額
景品を選ぶ前に、まずは全体の予算を明確にすることが大切です。景品代の扱いは会社によって異なり、飲食代や会場費を差し引いた残りを景品に充てるケースもあれば、最初から別途予算を確保している場合もあります。
予算が決まったら、景品の金額配分を考えましょう。上位2〜3割に豪華な賞品を設定すると、抽選やゲームがより盛り上がります。
たとえば、予算が50,000円であれば1等は15,000円の景品を1個、2等は10,000円を2個、3等は5,000円を3個、4等は1,000円を10個というように、メリハリをつけて選定しましょう。
参加人数
景品は参加人数に応じて用意しますが、全員に当たる必要はありません。限られた予算内で無理に全員分を用意しようとすると、どうしても景品の内容が物足りなくなってしまいます。
おすすめは、参加者の約3割程度に景品が当たるように設定することです。数を絞って、そのぶん魅力的な景品を準備することで、イベントがより盛り上がります。
もし予算に余裕がある場合は、上位当選者だけでなく、外れた人にも参加賞としてギフト券やお菓子などを配ると、全体の満足度が高まるでしょう。
男女比や年齢層
景品を選ぶ際は、参加者の男女比や年齢層を考慮することが大切です。たとえば女性が多い職場であれば、キッチン雑貨やインテリア雑貨など、おしゃれで実用的なアイテムが人気です。
ただし、コスメ類など性別が偏るアイテムは避けた方が無難です。男性が当選した場合に扱いに困ることがあるため、男女どちらが当たっても使いやすい景品を選びましょう。
年齢層が幅広く、選びに迷う場合は、誰にでも喜ばれやすい「万人受け」のアイテムを意識するとよいでしょう。
- グルメ系(高級肉や鍋セットなど)
- 家電系(ホットプレート、電気ケトルなど)
- 旅行券・食事券
- 生活用品(タオルセット、入浴剤など)
- 景品セット
ポイントは「自分ではあまり買わないけれど、もらうとうれしいもの」そして「持ち帰りやすさ」です。当選者のことを思いやった選び方が、会場の満足度を高めます。
景品の虎では、頑張る幹事さまを応援するために、さまざまな特典をご用意しています。さらに、全品ラッピング対応やお持ち帰り用の袋も無料でご提供していますので、ぜひ一度ご覧ください。
まとめ
忘年会の予約は、一般的に開催の2か月前となる10月頃が目安とされています。少人数の場合でも、開催日の1か月前までには予約を済ませておくのが理想的です。とくに年末はどの店舗も混み合うため、早めに計画しましょう。
さらに、余興やゲームに景品を取り入れることで、忘年会はより一層盛り上がります。
「景品の虎」では、人気アイテムはもちろん、予算別に選べるラインナップや、急な準備にも対応できる即日発送の景品もご用意しています。
さらに、当選者の自宅へ直接景品を届ける「商品引換券」対応も可能です。大きな荷物を持ち帰る必要がなく、参加者にも喜ばれます。そしてイベントの会場に商品がないため、見栄えや盛り上がりに欠けるということでおしゃれなパネルを用意しています。
忘年会を成功させる景品選びは「景品の虎」にぜひお任せください。